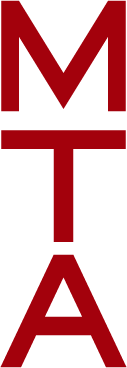Architect
東京サレジオ学園 風景の村、あるいは開かれた囲みの形式
新建築99年9月臨時増刊号
印象 10年目の雨
サレジオ学園を訪れた日は朝から小雨が降っていた。以前ここを訪ねたのは聖堂竣工の翌年、1989年の夏のことだったから10年振りの再訪となる。そのとき以来サレジオ学園の建築は、僕の記憶の一部に重たく残り続けていた。その重さは所以無きものではない。そこには建築物や養護施設というような社会通念を超えた、生そのものに向けられた眼差しや、特定の場所にだけ与えられた現場のリアリティーがあつたからだ。建築物を満たしていたものは単なる空気の軽さを逸脱していたからである。
それはわかっている。わかってはいるが、今日は朝から雨が降っている。そんな日に僕自身にとっても重いテーマを示唆する建築を訪ねるのは少し気が重かった。
なに建築には雨の日も晴れの日も晴れの日もありますからと編集者の大森さんは言う。
さすが職能人としての完璧な答えを用意しているなと感心もしながら、武蔵小金井の駅から車で10分あまり、サレジオ学園に着いた僕たちを出迎えてくれたものは雨のなかで更に鮮やかに緑の葉を広げた植物群だった。
10年の歳月は植物を成長させただけでなく、土地と建物を強く結びつけ、緩やかに起伏をつけられた敷地に配された施設群に、別世界のような心地よい環境を紡ぎ出していた。なんて素敵な場所だろう、そう思って施設に足を踏み入れた頃には、遠い国を旅行して目的の場所に辿り着いたときのように、うきうきした気分になっていた。
その後、建設時点での園長を務められていた現校長の村上神父、園長の野口神父、法人本部の関口さん、坂倉建築研究所で現場常駐していた大倉さん達に案内して頂き、改めて施設を観て歩いた。
偽らざるところ、雨の日に建物を観て、そのときのように気持ちよく、また、その気持ちよさの背後にある施設環境と、それを活きたものとさせている人の仕事が感じられたことはない。
大森さんはある程度それを確信していたのだろうか。いや確信しないまでも、晴れた日に見える美しい建築造形のみがこの施設群を際だたせているのではないことは間違いない、と考えていたことは確かである。彼にとってもここは、単なる建設物を超えた場所なのだ。
サレジオ学園の施設群は、建築物を超えた人間の生活空間を、誤解を恐れずに言えば普遍的な「家」というものの本質を人に想わせる力を持っているように思えるのである。
東京サレジオ学園の建築は、その場に足を踏み入れれば感じられることだが、単なる建築物として建っているだけではなく、運営する人、住んでいる子ども達、それともちろん建築物が、心地よい調和を保って場の環境を作っている。建築家の林昌二はその様な印象を「三位一体を目指す建築」と副題の付いた座談会の中で、三者のそれぞれの立場から持ち得た共通の目的という形で触れている。その様な点からも、建築にのみに偏った視点でこの施設を考えるのは正しくないように思える。そこで建築の内容に及ぶ前に、この施設が出来るまでの東京サレジオ学園の経緯について触れておくことが必要だと思えるのである。
東京サレジオ学園の沿革
東京サレジオ学園の営みは、日本の敗北によって戦争が終結したその年の1945年に、悲惨な境遇の孤児達を見かねたひとりのサレジオ修道会神父によりその準備が始められた。
翌1946年、ボランティアの手により、練馬区の成増にある旧陸軍飛行場跡地の兵舎を改築し、3人の孤児を収容して東京サレジオ学園が設立されたのである。
その翌年の1947年には、現在の東京サレジオ学園のある小平市に移転、小学校、及び48年には中学校としても活動を始めることになる。財団法人として出発した東京サレジオ学園は、養護施設を社会福祉法人に、学校を学校法人へと経営母体を変えて行きながら、その後も養護施設として社会福祉の前線で働き続けてきたのである。
戦争とその後の急な経済復興のなかで置きざりにされてきた子ども達を引き受けてきた東京サレジオ学園に変革期が訪れる。それは法整備に伴う法人の変更という様な社会の変化に対応するための外因的なものでなく1980年代に入った頃の学園内部から起こってくるのである。
それは、そこで生活する子ども達の処遇改善への要望を唱える職員の声として現れた。高校進学希望者の増加に伴う高校生の受け入れを一例とする養護状況の変化の中で、従来の大部屋横割り大舎制の養護方針が、「子ども達の家」という理念と乖離を見せ始めるのである。
当時のサレジオ学園の園舎は鉄筋コンクリート造で、子供達は、学校でもあるその建物の一部を借りて住んでいるような様子であったそうだ。
高校生の生活場所が限られ、二段ベッドを詰め込んだ「施設」としてもぎりぎりの、「家」とはかけ離れた状態に学園主宰者達は頭を痛め、事態の改善のために「東京サレジオ学園総合計画」をスタートさせた。
そして、ある縁から坂倉建築研究所の阪田誠造に、そしてそれから始まる一連の仕事を通して当時坂倉建築研究所の所員だった藤木隆男と出会う。1984年の夏のことである。
当面の課題は、高校生園舎の建設ではあったが、学園にとっては抜本的な養護方針の刷新への道を踏み出す第一歩となったのである。
アッシステンツァ「子どもに最善のものを」
養護方針の本質的な改革は、要約すれば集団から個へ、同年代の横割りグループ養護から異なる年代グループによる縦割りの、より家庭的な環境での養護、への移行を意味していた。しかしながら、長年培って来た方法論を捨て、新たな養護体制を画策する道のりは大変な努力と労苦の連続であったらしい。野口神父はそれを、今でも続く戦いであったという。
確たるノウハウや方法論はなく、試行錯誤の繰り返しだったのだそうだ。
建築家はこの段階で、幾つもの案という形で、サレジオ学園側の養護の理念の具体化に尽力した。
毎週辛抱強く続けられた徹底したヒアリングを通して設計者と運営者は互いの目指すべき方向性と、共に働く信頼を深めて行ったものと思われる。
ねばり強く、労苦をいとわぬ改革に彼らを向かわせたものは「子どもに最善のものを」という村上神父の言葉に言い尽くされている。
東京サレジオ学園の人々が考える養護の精神の根底には、サレジオ会の創始者ドン・ボスコの唱えるアッシステンツァ(支えるという意味のイタリア語)という理念があるという。
それはサレジオ会の大人達が子ども達を、養護や事業の対象としてでなく、修道会の生活を分かち合う本質的な要素ととらえることであるという。そのアッシステンツァの理念は、計画上のあらゆる局面で、労苦や手間暇をいとわずに基本的なスタンスに立ち戻り、何が子どもにとって最善のものか、を判断するという合意となって設計者、学園職員、等の計画に関わるすべての人々を結束させていったのである。
丹念なヒアリングとねばり強い提案
高校生園舎の工事のさなかに学園と設計者は第二期工事として小中学生園舎の計画に取りかかる。
設計者による丹念なヒアリングが続けられ、そこでの具体的な検討に備えて、今後の養護のあり方を策定すべく園内に「あり方委員会」と呼ばれた委員会が作られた。
より家族的なグループによる新しいタイプの養護を目指し、職員の勤務態勢や、食事の準備等、様々な予備的検討が行われたが、グルーピングや職員の配置等に確立した具体的な方策が決定出来たわけではなかった。第二期工事の設計で、現在の配置にいたるまでの検討は、度重なる建築家からの提案と建設委員会での検討、学園内部での徹底したシミュレーションを繰り返されたという。
村上神父はその過程を「学園の抜本的刷新」と題する文で触れ、自分たちの労苦よりも子ども達のためによりよい選択を、と考えた全職員の意識の高まりと、「ヒアリングという機会を通して、私たちと正面切って向かい合い、建築家としての信念を貫かれた設計者の並々ならぬ苦心と忍耐」無しにはサレジオ学園の改革はあり得なかったと記している。
その文中で村上神父は、配置計画上現在の中庭を囲む7棟に至るまでの提案は、段階を追って設計者側から提案されてきていることを明らかにしている。おそらく設計者の頭の中には、当初から抽象的な意味での「家」から「村」へ移行する連続する建築群のイメージが作られていたことは否めない。但し彼らは一足飛びにヴィジョンを振りかざすことなく、少しずつ少しずつ、運営者側の計画状況に沿って段階的に提案を進めたのである。
そして徐々に具体化してくる「家」や「村」の住形式を、運営者側も、決して偏見で拒否したり鵜呑みにしたりせず、徹底したシミュレーションを行い、様々な場合における、養護体制を「あり方委員会」等の場で検討し「どちらが子どもにとって良いものか」を考え、具体的なものとしていった。
やがて、建設当事者達のみならず修道会内部での変化も現れ、現在の配置案が実現するである。
村上神父はそれを「ときが熟した」と表わした。その「とき」は、設計者の能力だけでも、運営者の理解と熱意だけでももたらされれるものではなかっただろうと思われる。
相互の理解と信頼が、そして子ども達に最善のものを、という無償の目的を共有したことが、互いを引き上げあう「とき」をもたらしたのだろう。マスタープランの不在
東京サレジオ学園の建築計画は大きく分けて四工期に分かれて計画された。
第一期が高校生園舎の「譲葉舎」(ゆずりはのいえ)、第二期が、「ねむの舎」(ねむのいえ)、椎の舎、 (しいのいえ)ブナの舎(ぶなのいえ)、楡の舎(にれのいえ)、椽の舎(とちのいえ)、樟の舎(くすのいえ)の6棟の児童園舎と、「小聖堂」を併せ持つ管理棟「ドン・ボスコの舎」、厨房棟「カリタスの舎」、そして第三期が「ドン・ボスコ記念聖堂」と「地域交流ホーム」、第四期が「体育館」である。
設計者によると、第一期工事の「譲葉舎」の設計時点では、確たるマスタープランと言えるものは全くなかったという。
第一期工事の最中に管理棟を含む小中学生園舎の設計が進められたが、全体計画を下敷きにして進めるというものではなく、ひとつひとつの施設計画を進めて行く上でその都度配置計画が検討されたという。その段階でも三期工事となる聖堂と「地域交流ホーム」の計画は確定していなかったらしい。
各段階で製作された透視図には、募金活動の便宜上小さな聖堂と付随施設が描かれてはいたが、具体的には計画されていなかった。そのため、ほかの施設が出来上がってから具体化された第三期の「地域交流ホーム」「ドン・ボスコ記念聖堂」の配置計画は楽には納まらなかったそうである。
それぞれの建築あるいは工期毎に施設全体を見た場合、やはり、決定的なピリオドは第二期工事の小中学生園舎、と管理棟の建設であったと言えるだろう。
第一期工事、譲葉舎で、プロトタイプ的に示された建築的解決法が、第二期で具体的な回答となり、複数の建築群と、一体となった外構計画を伴う全体計画として実現するからである。
第三期工事は聖堂、地域交流ホームが、第二期工事から施設の計画に参加していた方圓館の家具、横尾龍彦の彫塑、イワタルリのガラス工芸等、各方面の作家達のコラボレートを得て完成する。いわばサレジオ学園のものづくりの頂点として位置する仕事である。
そして阪田誠造が自ら終楽章と呼ぶ「体育館」を第四期として建築的オーケストレーションは完結するのである。後に藤木隆男が坂倉建築研究所を離れ、別の立場でサレジオ学園小学校、中学校の校舎を手がける事になるが、坂倉建築研究所の四期にわたる建築群とは、様々な共通点や、引き継がれたものは少なくないが、やはり別個に論じられるべき建築であるだろう。
デザインされた地形
配置計画の中で、学園側が設計者に強く要望していた条件に、決してグラウンドを削ってはならない、というものがあったそうである。広々とした学園の敷地ではあるが、第二期工事の全体計画を受けての地域交流ホーム、聖堂の計画は配置上楽には収まらなかったそうである。しかし、用地を限ったことにより、建築群は平坦で広々とした学園の敷地内に、ある種の架空の地形を作り出しているかのような効果を上げている。
また実際、小中学生園舎群によって囲まれた中庭には、盛り土により穏やかな起伏がつけられている。経済的な残土処理という理由もあるらしいが、建築物の内部にいるときに体感できる、低い庇の線と、芝生に覆われた中庭の穏やかな起伏が作る固有の空間は実に安らいで気持ちが良く、地形という「作られた自然」がこの建築群の重要な構成要素となっていることを物語っている。
管理棟の建築物が二棟三ブロックに分けられて、地形を暗示するような曲線に沿って僅かに折り曲げられて配置されていることも、「ドン・ボスコ記念聖堂」が連続する「地域交流ホーム」に対して振られて配置されているのも、見えざる地形を見えるものとする一助となっている。そして地形はまた人の歩みによっても示される。建築物の間に緩く曲がって各施設をつなぐ散策路は、その線形によって地形を見えるものとして建物に結び付ける。緩やかに弧を描く「地域交流ホーム」のコリドールは集会室のホワイエともなっているが、中庭を囲む生活空間である家々と、聖堂のエントランス広場との間に適度な距離感を作り出すしつらいでもある。僅かに曲げられたアプローチや緩やかに起伏を付けられた地形は、そこを歩く、あるいは見るものにとって、物理的な広さや距離にもまして想像力や意識に働きかける広がりや距離感を作り出す。そこにはのびのびとした広がりと居心地の良いヒューマンスケールは何の矛盾もなく共存している。
「地形」と建築への配慮は第四期工事の「体育館」までにも及んでいる。
グラウンドのレベルより僅かに低く沈められ、ずらされた壁面構成の美しいプランを持つ体育館は、マンサード屋根とされてスケール感の連続性を断ち切らないように軒を低く伏せられている。その低い軒先周辺の地表レベルは建物に向かって盛り土され、持ち上げられて建築物のスケール感を和らげている。外に向けて開かれた屋根の庇も、見る者の視線を水平に切り取って地形への連続を促すのである。
予定調和の風景
第二期工事が終わる頃にも、未だその計画すら確定していなかった「聖堂」と「地域交流ホーム」が出来上がってみると、あたかも初めからすべての計画がそれを予想して、そこに収斂していったかのようにも見える。すべての建物は、初めに描かれた小さな街か村の情景を目指して建設されていったかのように思えるのである。
その情景は建築家と共に視察に訪れたドイツ、ベンスベルグのG.ベームによる「子供の村」(1912-67)や、同じ建築家の「ネヴィゲスのカトリック教会」(1962-64)と教会施設の配置が作り出すアプローチの空間にも見ることが出来る。それは、丘の頂に教会を建て、そのまわりに取り付くように家を作り、人々が寄り集まって住まう村、もしくは小さな都市のある風景なのである。
特に教会を中心に持つ小舎制に基づいた養護施設である「子供の村」では、先進の養護計画にもまして、柔らかく配置されたヒューマンスケールの外部空間に、運営者、設計者共に触発される物があったという。
G.ベームは前述の二作品の他、「ベンスベルクの市庁舎」(1962)等の作品でも、頂に立つ建築と、丘の等高線に沿って塔を囲むようにして建つ建築群によって、アプローチとなる囲われた広場を作り出している。
しかしそれらの配置計画は、周到に意図されたものであっても、ヨーロッパの城砦都市や山岳都市の一部にその原型を見いだすことが出来る。
丘の頂に建つ城と聖堂の廻りに、独楽に巻き付けられた糸のように、螺旋形を作りながら寄り添いひしめき合って建つ住居とその間の街路が、そこを歩く人に、ときにはタイトに、ときにはゆったりと広がって作るシークェンシャルな空間がそれである。
サレジオ学園の建設において、設計者のみならず施設運営者たちも、徐々に囲われて緩やかな起伏を見せる中庭に、丘の教会を囲む家並みが作る村の情景を思い描き、それを逆に辿ったのだろうか。
それらの、新しく作られた現代の建築群でありながら、ある意味で類型的な村を思わせる全体計画の様相は、マスタープランと呼ばれるものの有無を超えて、あたかも予定されていたかのような調和を見せるのである。
開かれた囲みの形式
東京サレジオ学園の建築とそのしつらいを個別に書き尽くせば、いかに多くの紙面をもってしても到底十分とは言えないだろう。従ってここではその個々の読み解きには触れず、むしろそのすべての計画の中に見られるある建築的な構造、強いて言葉にしてみれば「開かれた囲みの形式」とも呼べるようなものについて触れてみたいと思う。
譲葉舎は坂倉建築研究所の手による東京サレジオ学園の施設の中で初めに建てられたものであり、ある意味で最も完結したものであるとも言える。恐らく計画の着手時点では四期に至るまでの全体計画の実現に何の確約も無かったためであろうし、目前に高校生たちの家を作るという急を要する具体的目標があった為でもあっただろう。しかしその計画にはその後に展開される建築の「あり方」が垣間見えるのである。
まず、中庭である。案が決定された際のスケッチにOutdoor Liv.家の中的空間、と記されていることからも、その部分が中央部の余白ではなくその建物で最も広い部屋、として計画されていたことがわかる。実際の建物でも特徴的な、内外の床仕上げを面ぞろに仕上げ、引き戸を壁柱の後ろに完全に引き込んで隠し、内部と外部の境を消し去ろうとするディテールはその段階のスケッチにすでにはっきりと表されている。
また、中庭は、ブルネレスキの「オスペダーレ・デリ・イノチェンティ」のファサードを思い起こさせる腰高な立面を作る打放しコンクリートのフレームで部分的に囲われている。
中庭を規定するそのフレーム状の壁柱も個室を繋ぐ二辺で入隅を作り、強く中庭のボリウムを規定しているのに対し、中庭と一体化すべき居間の部分は丸柱とされて内外の連続感を保っている。
決定案のスケッチでは、きっちりと形式的に規定された内側に対し、建築の外周部は個々の内容からの必要性によって自由に作られている。実施案でもコの字型から飛び出した浴室や機械室が、現れることからも、ボリュームの構成においては決して完結したコの字型やロの字型を目指しているのではないことは明白である。むしろ、デッキや壁柱のフレームを「つなぎ合わせる装置」として用いながら、建築物の各部内容に応じた部屋や設備を複数のクラスターとして統合して行く意志が読みとれる。
そしてこの建築物に明らかにある種の異物として挿入されているのが、中庭の最後の一辺を押さえる音楽室である。
決定案のスケッチでは、音、アトリエ、洗タク、等の役割を与えて、比較的強い線で、しかし周辺を決めきれない何物かのボリュームが描かれている。その上部にはパーゴラが描かれ、中庭をどのように閉ざすかを自らに課題として課した痕跡が見て取れる。
実施案では中庭側に壁柱のフレームが取り付き、中庭の一辺を決めてはいるが、外部ではフレームは、理由としてはサービス用車両の出入りのためか完結されておらず、壁の連続は内部の間仕切り状の壁につなげられる。
これにより中庭の矩形は二つのずらされて向き合うL型となり、内外の領域を更に融合させる。音楽室の特異な立体と、その上に掛けられた葡萄棚は内部的な外部の中庭を曖昧に閉ざし、その外にある本当の外部へと柔らかく繋ぐのである。
その様に見て行くと、古典的な道具建てによって構成されている囲み配置の建築物でありながら、クラスター分けされた部分のボリュームやずらされてダイナミックに構成された壁等の組立方が以外にモダーンであることに気付く。
内容的にはある意味で正反対で形も異なるが、完結したクロイスターを持つ修道院の形式を逆転し、彫塑的な立体と併せて再構成したコルビジェのラ・トゥーレットの修道院のプラン構成を思い起こさせる部分もある。囲いの形式は決して完結しないのである。
それは坂倉準三の仕事を継承する坂倉建築研究所の根底にあるモダニズムの遺伝子なのか、それともコートハウスの空間に対する阪田誠三の独自のスタンスでもあったのだろうか。
第二期 フレームが囲う中庭
そして、開かれた囲み型の建築は第二期工事の中で、複数の建築群と地形によって具体化される。
個々の住居は一階を居間食堂、設備諸室等の共用部に当て、二階に寝室を設けている。それぞれの園舎はやはり床のレベルに合わせられたテラスを持ち中庭へと開かれている。
テラス側のファサードには、譲葉舎で中庭を囲んでいたような打ち放しコンクリートのフレームが取り付いている。それが個別の家同士を結びつけ、一体のつながりとして中庭の周辺を押さえている。もっともスケールやピッチは「譲葉舎」のそれと比べると小さめのスケールに納められた園舎と穏やかな起伏をもつ広い中庭を結ぶ為に、より低く、より広い間口とされている。
6棟の小中学生園舎の中で小学校一二年生の為の専用園舎である「ねむの舎」だけは平屋で、大きな中庭につなげられていない、建物内部で閉じたデッキ状の中庭を持っている。「ねむの舎」は、建物内部にレベル差を付けられており、その中庭はレベル差に合わせて階段状に構成されて、もちろん室内空間と一体化して計画されている。
これは、低学年の生徒だけが、シスターの手によって優しい雰囲気の中で保護され育てられる事に向けられた配慮である。計画当時は、三年生になった生徒たちは他の五つのそれぞれの家に分かれて新しい生活を送ることになっていたが、最近は「ねむの舎」も6つめの家として多年代の家族的なグループの家として用いられているという。
開かれた囲み型の建築群は、特殊な地形を連想させる管理棟によって、より演出的に表現される。
特に長く低い壁面を背景に水面に浮かべられた「小聖堂」は、水面に映る光を取り込んだ美しい内部も素晴らしいが、中庭に対しては、特別に祝福された場所であることをを暗示するピクチュアレスクなオブジェともなっている。
アナロジカルな符合
様々な配置の検討を経て定められた第二期工事の構成は、意外にも与条件も構成単位も異なる高校生園舎「譲葉舎」の構成に重ねられる。
実施案も大筋では変わりはないが、最終案のスケッチが最も明快に対応関係を示している。
乱暴なアナロジーを駆使して「譲葉舎」の原案を配置上左に90度回転させて、高校生園舎の個室群を小中学生園舎に重ね合わせると、食堂とリビングの位置は「ドン・ボスコの舎」の居間、食堂、ロビー部分と照応する。「カリタスの舎」は、もちろん厨房と職員室である。そして、ピクチュアレスクな「小聖堂」のしつらいは、スケッチにおける暖炉なのである。
それらは「安らかな家」と、(教会を囲み、信仰する)「人々の村」それぞれに向けられたイコンと見ることが出来る。
すると「ドン・ボスコ記念聖堂」と「地域交流ホーム」はパーゴラや音楽室という、「譲葉舎」では外に開かれていて、なお中庭を柔らかく規定する「異質」な造形要素で無ければならないはずである。そして植物の蔓にびっしりと覆われて、視覚的には中庭に解放された「地域交流ホーム」の集会室や、弧を描く列柱のポルティコの中を歩いていると、その予感は確信に変わる。
野に集う人の教会
そして、聖堂に足を踏み入れたとき、特異な造形要素である聖堂に、それまでのサレジオ学園のすべての建築がよって立っていたあるひとつの事柄が、見事な建築造形と美術工芸によって具体化されるのをわれわれは目の当たりにするのである。
それは、原野に集って空と大地の間で作る人々の環がつくる「場」を空間の原質とし、建築はその人々の場を特定の場所に留めるためのひとつの、けれども統合的なしつらいであったということなのである。僕は長い間、サレジオの聖堂に「屋根」がないのが不思議だった。シンボリックな塔を傍らに持つものの、通常であれば信仰の中心となるべき聖堂は、大伽藍の偉容を示して不思議はない、それにしてはその聖堂は、帽子の箱のようにそっけない。しかしそれはそこを特化された外部と見ることにより理解し得るのである。
阪田誠三は、「秘跡の儀式の空間-聖堂について」と題する小文の中で1962年から65年にかけてのカトリックの改革で「教会建築は人格主義への転換を意図することとなり、(中略)多中心の集中空間が望まれるようになった。」と記している。
そしてその具体的な答えのひとつとして「野に集う人」の教会を建築物の内部に作り上げたのである。
室内の壁面の一部にはドイツの教会の屋根などによく用いられる、シーファーと呼ばれる天然スレートに似せたいぶし瓦が用いられ、格子梁の天井とその壁面の間にはトップライトが設けられ壁に外光を落とす。ここは裏返された外部なのである。
荷を担わぬ壁はオーロラのように豊かなドレープで人々を包み込み、空気を遮断していたガラスが引き上げられれば、外の内陣と名付けられた囲い庭は、言葉の上からは内の外陣とも言うべき聖堂と一体化されるのである。ガラスの聖櫃はそのときに最も美しい光を纏って野に立つ、そして空間は建築化された庭園となるのである。
庭園の建築
庭園という考え方は、この施設群を理解する上で欠かせないもののひとつであるように思われる。ひとつは「地形」という施設のデザインであり、また、花や樹木等の植裁もその範疇にはいる。庭園論を著した西沢文隆亡き後も、植裁の素養は坂倉建築研究所に脈々と引き継がれて来たらしい。
植物好きの関口さんは坂倉建築研究所の現場常駐者との「植物知識比べ」について楽しそうに語った。譲葉に始まり、ねむ、椎、 ブナ、楡、橡、樟、とすべてに植物の名が付けられた園舎もまた、竣工後10年あまりを経た今は、すっかり成長した樹木と絶妙な調和を見せている。
いつも手を掛けられている窓台の花はとても美しく、あまり使われない玄関のウッドブロックの間には、雑草が茂っている。子供達はテラスと、洗濯場に近いサービス口から出入りしている。
裏口から帰ってくる子供達は、良く整備された施設背後のサービス路を自転車で走ってくる。
あまりにも穏やかな中庭側に対して、ガスボイラーや、自転車置き場のある、アスファルトのサービス通路側に出ると、普通の世界に引き戻されてちょっとばかりほっとする。緑豊かな、囲われた地形を作る建築的庭園の背後に、きっちりと充実したサービス動線が計画されていることも見逃せない設計者の仕事なのである。子供達も裏が好きで良く遊ぶのだそうである。それが普通の子供なのだ。
家の形象
サレジオ学園の園舎の設計に際して、設計者は高校生園舎の計画時点から、小中学生園舎の建設にまで、一貫して「家らしい家」を表現している。
たとえば、吹き抜けの階段に絡めた暖炉のあるリビング(譲葉舎)、イタリアの街並みを思わせる瓦を載せた切妻の勾配屋根、花を植えられた窓台など、普通の住宅を思い浮かべ易い具体的な要素が積極的に取り入れられている。但し、譲葉舎の暖炉の廻りにせよ、オーディオや花を置かれた小中学生園舎のリビングの壁面にせよ、目地による巧みな分節や注意深い開口を持つコンクリートの打放しにより非凡に作り込まれており、決して紋切り型に収まってはいない。
内装素材もコンクリートの打放し、パーケットフロア、木製の建具や家具、AEP仕上げの壁等の質素で飾り気の無いものに限定されているが、丁寧に作り込まれたディテールと慎重に決められたプロポーションにより、暖かみのある豊かな空間を作り出している。
園舎に関する限り、建築物の外観はのどかな村の家並みとして風景にとけ込んでいる。
第二期工事の園舎各部は、「譲葉舎」の各部デザインや素材を引き継いでいるが、まったく同じというものはなく、少しずつ手を加えて用いられている。ヴォーリスの「神戸女学院」に触発されたという屋根瓦も、全体はオレンジがかった黄土色の印象を与えるが、細かく分けされた6色の混成パターンになっている。配置からディテールに至るまでの、各部に共通することは、単純だが単調でない穏やかな連続感と暖かみである。
特異な形態表現や素材感の主張を遠ざけ、解り易くピクチュアレスクな「家」の形象を求め続けたことが、この施設を単なる建築群を超えた「庭園」の高みに引き上げるのである。
その庭には美しい聖堂や木々を背景にしていつも穏やかで暖かい村の風景が映るのである。
よりよく、より豊かに
小雨は絶え間なく降っているものの、空は比較的明るい。建物はすべての窓を開け放し、気持ちよさそうに深呼吸をしている。内部にいる僕もなぜか呼吸がし易い。
光と水と木々の緑が建物と交感していて、中にいる人々もその恩恵を受ける。
サレジオ学園の建物は、つまりそんな建物なのだ。だから豊かで気持ちが良い。
そこにいれば、少し先の雑然とした既成市街地や、通り抜けてきた街の喧噪すら忘れてしまう。
10年前、人々がじきに来るバブル崩壊も知らず乱舞していた頃、この建築群は静かに生まれたのだった。そして今も、何事もなかったかのように穏やかで美しい佇まいを見せている。
多様性や、数限りない選択肢、無限の可能性と言う名の袋小路をこの建築は、この人々は選ばなかった。「家」という原点に立った建築と、人の仕事を選び、様々な理由のつく一般解を捨て、今その場でしか出来ない具体的な解決を選んだ。そして豊かな環境を獲得した。
ひとつの小さな仕事や場所を通じてしか、人は豊かな世界に辿り着けないのだろうか。
すべてに手が届きそうに見える、焦燥と欲望に満ちた都市の雑踏は、此処では感じられず、ただ静謐で美しいだけである。地道で現実的な努力の先に、必ずより良いものが来ることを信じて働いた、人々の仕事の痕跡がここには満ちている。しかし、ときとして影のない穏やかな環境に、自分がそこに居続けるには眩しすぎるような居心地の悪さを感じもした。
恐らくそれは、その場を作り上げたすべての人々の、過剰なまでの意志で作り込まれた、平穏な「家」または「村」の幻想が与えるものなのだろう。
そしてそれらのイメージがことさらに強く表現されねばならない理由が、そこに生きる子供達の担う、家族や家の絶対的な欠落にあることは確かなことだ。
ここはただの生活環境ではない、他人同志が集まって作った「家」なのだ。
そして、建築を越えたよそ様の家で自分の居心地などを考えたことを僕は少し恥じたのだった。