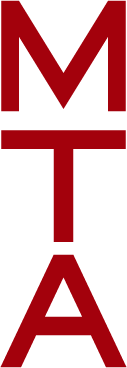Architect
建築の代用品
住宅特集95年10月
『SD』1973年5月号は僕にとって特別な建築雑誌だった。
18歳の僕はその雑誌で、それまでどこかでその名だけ聞いていた、ハンス・ホラインというウィーンの建築家の仕事をはじめて知った(余談だが同誌上で、美術評論家の針生一郎がクリストの紹介をしている。一連の梱包の仕事は当時もよく知られていた。が、その記事で当時をさらに3年遡る、1970年の都美術館で見た光景が改修工事でなかったこともはじめて知ったのだった!)。いまだにその雑誌を開くと、当時の鳥肌立つ思いでページをめくった記憶が蘇る。傾倒していた世紀末のヨーロッパ文学や、シュールレアリズム、ミニマリズムの美術や、当時、相次いで出版された大きな影響を受けたバタイユの著作や、だんだん具体的になっていきつつあった建築に対する関心。そんなさまざまな興味と焦燥感の彼方に、ホラインのアイロニーにあふれ、かつ美しい建築の謎掛けが示されたのだ。
磯崎新、中原佑介、多木浩二の3氏が文を寄せている。3篇の文のタイトルに共通する単語が見られる。「死」という単語である(ちなみに助詞を除いた残りの単語は、祭儀、思想、物体、それと建築家の名前のみである)。いくつかの建築的作品に並んで、コラージュによる観念的なプロジェクトと多くの展覧会の記録は、生々しい死の香りをそれほどまでに放っていた。淡い光の中を浄土にフェイドアウトしていく、生死の連続する仏教的なそれとは異なり、原色の光を統合した白く強烈な光を一瞬にして暗転させるような断絶であった。「すべては建築である」という、たちどころに無意味と化してしまいそうな言葉の背後に浮かび上がるのは、「死」や「断絶」に縁取られた「自我」という主体だったのだ。
その後20数年を経て、その建築家も多くのポスト・モダン作家の中に肖像を連ねられてしまった感もある。またわれわれも、自我や死について考えることを、何か「時代遅れ」のことに対するような疎ましさを感じて長く忘れていたのである。長く忘れているうちにわれわれは、社会が役割としてわれわれに与えた人格、つまり夫や妻、父や母、学生、会社員、主婦、建築家などのカテゴリーと自我との界をだんだんと見失い、気がつけば社会を埋め尽くすさまざまな物品の特定の「利用者」「オーナー」として、自ら物品と同等のセグメント設定に納まってしまったのである。
僕がここで建築の代用品と呼ぶ物は、われわれの心身を取り巻く環境に集められたすべての「物事」〈matter〉のことである。ただし、われわれの心身とは絶対的な意味での「自我」とは異なり、ジェンダーや職業によってカテゴライズされた社会人的人格のことを意味している。ある意味で疑似主体といい換えてもよいかもしれない。そして、物事とは社会的人格に目的として提供される「意味ある物事」のことなのである。主婦のキッチン、夫の書斎の類いである。ビジネスマンのシステム手帳や女子高生のポケベル、自動車や衣服まで挙げれば具体例は無数といってもよい。代用品(モノ)が代用主体(ヒト)の充足に当てはめられるヴァーチャルリアルな関係、ともいえるだろう。それゆえにホラインのいう「建築」は現れない。やはり代用品なのである。ホラインが、自分の主体性をどう信じていたかは定かでないが、少なくとも「建築」〈Architektur〉という言語のもつ特定の概念を「すべて」(の現象)と対応させることにより固定概念の解体を図ったのだ、とはいえるだろう。それに対してわれわれの建築は、自動車の構造的なパッケージングやコンピュータのシステム構成等にも使われる“architecture”の代用語として近代日本が、主に建造物、あるいはその建設を扱った学問を西洋から導入する必要に迫られてつくった言葉である(注1)。したがって建築とは鉤括弧でもつけない限り、この100年余りに近代国家の興隆を文字通り築いてきた建設上の現象、あるいはその背景となる知識等を差す実用的な専門用語なのであって、解体を図らなければならないほどの文化的コンプレックスを成してはいないのである。つまり、歴史の中で具体的な都市や建築物から経験的につくられてきた、言語のように保守的なコードをもち得てないのである。保守的な足枷をもたぬ分、身の軽い建築産業は数多くの建築の代用品で都市を埋めつくした。
その結果、60年代のウィーンでホラインが解体を図らなければならなかったコンプレックスは、姿を変えて90年代の日本で、具体的な物の堆積として現れたのである。
建築概念の混乱はよく語られるが、観念的危機感より困ったことは、今そこにある建築(タテモノ)の混乱なのである。建築物は具体的な環境のみならず、経済行為や人の心身に直接影響を及ぼすものだ。それらのいわばプラグマティックな問題は、個々の建築の現場に置き去りにされ、建築家が観念的な危機感しかもてなくなってしまったとすれば、それこそ建築という代用語の自縄自縛というよりほかはない。
「建築物」の周辺
われわれはさまざまな物に囲まれた環境の中を生きている。とりわけ身体的な空間を覆う建築物は、われわれの環境にとって支配的な影響力をもつものだ、と考えられてきた。建築は物的密度の高い環境を、その内部に対しても外部に対してもつくり出す行為であった。したがって特定の場所に特定の建築物が建設される、ということは、物理的環境への影響も少なくないが、また社会環境にとってもその建築の建て主であると利用者であるとを問わずに、さらにはその周辺の人びとにとってもかなり大きな事件であり続けてきたのである。その半面、経済社会の中での建築は建設や売買という経済行為を通じて、個々の建築物や人びとが場所と結ぶ固有な関係としてよりも、流通可能な一般的耐久消費財〈しょうひん〉としての資質をももっているように思われる。自動車のようにモデル別に販売(建設)される住宅をはじめ、通常の設計と建設による建築物ですらたいていの場合「引き渡し」という出生の儀式を経た後は、解体に至るまでの寿命を消却される耐久消費財〈しょうひん〉ともいえる使われ方を強いられるのである。
大戦の焼け野原から50年を経て、われわれの物的環境は急速な発展を遂げた。工業生産の拡大を背景にした経済的な拡張は、日本中に大量の物を送り出してきた。家電製品や自動車等の工業生産品はいうまでもなく、都市部の建築現場は景気の変化による増減こそあれ街の見慣れた風景となり、その結果視野に入るほとんどの建造物は、この数十年間に建設されたものとなった。さらにその間にすでに寿命を終え、新たに建て直された建築物も多く、時にはそれ以上もの回転で建設が行われてきたのである。常に街のどこかで続けられてきた建設や解体を見るにつけ、多くの人びとは建築物を目的に応じた1回使い切りのものと考えてきたのである。建築は、その場にあり続けるものではなく、必要に応じて要求されるものとなった。建設されるにせよ、そのために解体されるにせよ、いずれにしても経済的、社会的な時代の産物となったのだ。建築は、その内容や使い勝手とは無関係に、特定の場所や環境に対して成り立つ文化的に共有し得る行いである以前に、社会的目的をもった生産物だとする見方が一般的になった。建築はその(1回使い切りの)用途に即して、住宅や病院、舞踏場、倉庫等のカテゴリーに分類され、その実現の方法に至るまでいくつかの類型に分けられた。そして、カテゴライズされた類型は制度化され、建築基準法として制定されもしたのである。
このような事態は、建築に寿命や耐久性といったような「耐久消費財」としての見方を定着させただけでなく、物的環境をつくるに支配的であった建築から、自動車や衣服、家電製品などほかの流通する物との間にあった垣根を取り払ったのである。もはや建築は、物のつくり出す環境の中で、特別なものではなくなったのである。都市や環境の具体的な一部分であったはずの建築は、社会的な用途と目的に応じてその都度提供される架空の実用品となったのである。固有の建築が、制度や類型の中で「意味ある物」となっていくとき、われわれの身体の周辺に残された物の累積は、よき時代の建築の代用品となったのだ。
建築の喪失
日本中のリビングルームをニュースショーの客席に変えた、オウム真理教の報道は、連日頭に番号を振られた「サティアン」と呼ばれる建物の映像をテレビの画面に送り続けてきた。中でも第7サティアンは、事件の核心に触れる建造物として話題となった。実際そこは化学プラントでもあったのだが、工場か倉庫に類する無表情な建造物は宗教建築物の先入観をもった目に、きわめて異様な風景と映ったのだった。至聖所と化学工場の同居というのも前代未聞だし、だいたい宗教的に特化された場所であれば通常の感覚では、何かそれが建築的にでもあるいはせめてサインだとしてでも、建築物に表されていそうに思えるものであるのだが、第7サティアンには工場とは連想できる密集したダクトがあるばかりで、宗教的な印象を人に伝えるわずかなそぶりもなかったのである。信者が自分たちの手で建設し、必要充足の手段としてのみ用意された「無意味」な建造物は都市近郊部の工業的建築物にありがちな実に殺風景なものであった(注2)。そこには、社会的、文化的な空間をつくり出す建築は必要とされていなかったのである。そして、統制された身体と精神の用法とドラッグがその空間を満たしていたのである。ハンス・ホラインのノン.フィジカル.エンヴァイラメント.ユニットのマニフェストは、予言となって成就されたのである。
建築を映す鏡
それを「建築」とは無縁の特殊な出来事として無視することも可能である。しかしながら、無視するにはあまりに切実なわれわれ自信の置かれた建築的状況が、極端なかたちで写し込まれてはいないだろうか。よかれ悪しかれ、建築は社会の欲求によって実現させられるなら、建築は社会を映す鏡ともいえよう。そして、逆に現代社会の多様性こそは「建築」を映す鏡となるのではないかと思われるのである。よほどの脳天気な人でない限り、現実の社会の中で「建築」の実現を思って手を汚した経験をもったことがあれば、建築がそれ自身の価値で成り立っているイノセントな文化的行為だ、と信じている人は稀であろうと僕には思えるのである。
19世紀のリアリズムに対する嫌悪は、鏡に自分の顔が
映っているときのキャリバンの怒りである。19世紀の
ロマンティシズムに対する嫌悪は、鏡に自分の顔が映
っていないときのキャリバンの怒りである(注3)。
オスカー・ワイルド
そして20世紀のバラック宗教建築が見せるグロテクスさとある種の寒々しさは、現代社会の中でつい日ごろ目を背けているわれわれ自信の置かれた建築的境遇を、ことさらに現されることに起因するのではないかと僕は考えている。
建築のロールコンプレックス
そして、ドラッグと洗脳の背後で意味を失った貧しくも即物的な建造物群が見せるものは、現代社会の中の経済機構や流通可能な価値観を離れては建築物がその役割を見い出せずにいるロールコンプレックス(役割喪失がもたらす葛藤)への不安なのではないかとも思われる。われわれを取り巻く建築環境の、ある種のカリカチュアともいえる施設の中で暮らす人びとにとって宗教と薬物はフィジカルな環境に代わるものだったとすれば、建築は疑似環境を囲った箱にしか過ぎない。そして現代社会で生活し、ドラッグのような有効な代用品をもたぬわれわれは、気づかぬうちに多くの代用品によって自分の環境を埋めつくしているのである。空調機や暖房等の機械設備はもとより、再生される映像や音楽、おびただしい量の情報、電子機器、ダイエットやビタミン剤、住宅産業が育て上げてきた夢いっぱいの生活像にパズルのように当てはめられた商品群、これら多くの叶わぬ夢の代用品は、われわれの日常を取り囲み、閉じこめられた箱の中に疑似環境をつくり出すのである。そして、さまざまな役割を与えられた建築の代用品が、その役割を失うことをわれわれはいつも恐れているのである。
物、身体、行為
われわれの環境を埋め尽くす、物にはさまざまな役割が与えられている。その役割の多くは、われわれの身体の使い方と結びついたものである。人は椅子に座ってベッドに横たわり、ドアを開ける。物と結びついた当たり前のような日常的行為も、人が生まれながらにもっている能力と異なり、言語と似て社会的人間となるために教育されて身につけるものなのだ。子供のときに椅子をひっくり返しちゃいかん、とかベッドに飛び乗るな、とか親にしかられたことは誰しも覚えがあるだろう。ましてや自分で子供を育てた経験があれば、家具や家電製品に対する子供の想像を絶する振る舞いに思わず感心してしまうこともある。物と結びついた人の立居振舞いは、あらゆる日常生活に始まって食事のマナーやスポーツ、お茶や宗教的な儀式に至るまで広くわれわれの生活に結びついている。
物にかかわる個人的な習慣や身についた躾(それがよかろうと悪かろうと)は、客観的なものでないだけに一般論としては頷けた話が細部に至ると理解不能になることも多い。住宅の設計をする場合、施主のフェティッシュなまでの身体的な習慣によって、数多くある解決の選択肢をことごとく否定され、辟易とした設計者の方も多いのではないだろうか。身体は物にかかわるとき決して公平ではない。フェティシズムの対象は、細部にいけばいくほど僅かな差に厳格な選択を下すものである。コードやマナーの共有は可能でも、物に直接かかわる身体的な体験の共有は不可能だ。そして、その共有の不可能性のゆえに、人は物とエロティックな関係を結ぶことができるのである。
しかし物の体験の不連続性は、個人を覆い隠すものではなく、個人の手に属する芸術表現はもとより、楽器の演奏やスポーツでは規範をもって高められた技術は、その背後にある「主体」をより一層露にするのである。身体的空間、とはしたがって自由な空間を意味しない。身体を拘束するコードとそれにかかわる(行為を行う)主体が出会うところに生ずるものだ。それは不自由で不連続な空間ではあるが、人はそれを共感することができる。
記憶と情報
身体や行為と結びつけるものは、身体にプログラムされたコードと肉体的な運動だけではない。それを共有する社会の中でつくられた物のかたちの中にも同様なコードが潜んでいる。たとえば椅子である。人は座るために椅子を用いるが、逆に椅子という物のコードに沿って座るという行為を行うのだ。
身体空間は運動を伴って経験される空間である。従って、空間とはいうものの時間的な要素を大きくもっている。日常的な行為の時間から場所や特定の出来事とのかかわりに及ぶ長い時間まで、身体空間がかかわる時間は多様である。建築物や都市の一部には、記念碑のように歴史的に特定された時間と場所を記録するものもある。しかし、ひとりひとりの身体的時間や記憶にかかわり固有の空間をつくり出していくような時間は、そのようなモニュメントが示す、点の時間や事件のみを必ずしも意味するものではなく、懐かしさや漠然とした居心地のように曖昧な感覚や、癖のように身についた立居振舞いなどの中にも潜んでいるのである。85年のウィーンで開催された「夢と現実 ウィーン1870-1930」展は、世紀の変わり目にあったウィーンに繰り広げられた文化、芸術活動と歴史的背景の記録である。個々の美術や工芸の展示もすばらしいものではあった。が、それ以上にポスト・モダンと呼ばれた世相のただ中にある85年現在のウィーンに対して、その状況の端緒ともなったモダニズムの胎動期から黎明期にあった都市を、さまざまなジャンルのドキュメンタリーとして相対的に提示し対比させたという点で画期的なものだった。ハンス・ホラインの開場構成もあざといばかりに心憎く、大きな扇風機の風にマントをたなびかせた首のない甲冑の騎士の居並ぶ階段を登って、フロイトの1900年の著作『夢判断』を展示した部屋に入れば、本の入ったケースのみがわずかに照らされた暗い部屋の片隅の天井付近に、ブラックライトに照らされ小さな金色のベッドが象徴的に飾られているというような外連味〈けれんみ〉に溢れていた。
これはウィーンという都市〈マチ〉でしかできない展覧会だと思った。都市の記憶と呼べばあまりに擬人化したロマンチックな響きに聞こえてしまうが、時代を超えたコンプレックスを常にストックとしてもっている都市ではじめてできることだ。その固有性を信じて疑わない市民が1個1個の細胞となって固有の都市のコンプレックスを保存し続けているのである。「夢と現実」というタイトルも、音楽や演劇、絵画、建築などの文化的側面に対し、第一次世界大戦の影を落とした世相や世界恐慌、第二次世界大戦へと向かうナチスドイツの台頭等、都市〈ウィーン〉を背景にした社会現象を並んで示すことにより、歴史の二重構造的な部分を問いかけたものだ。それは、人の意識と無意識のように不連続なものの共存なのだろう。そしてそれが都市を魅力的なものにしているのだと思う。
ウィーンのような都市は、人や物によって特定の場所に固定された「記憶」のようなコンプレックスが深く染みついている。翻って物に溢れたわれわれの都市は、その細胞ともいえるわれわれと共に記憶のコンプレックスをもち得るのだろうか。建物を特定の場所に固定する杭のように、人の意識を無意識とつなぎ、固有のものとするものが記憶という錨〈アンカー〉だとすれば、自己の固有性を確認するために記憶は大きなよりどころである。それに関して大学で教えている建築家の友人から興味深い話を聞いた。最近の学生世代の人たちは、記憶という言葉がどうもピンとこないらしい、つまり、受け入れた情報や知識との区別がイメージできないようなのだ、というのである。それを聞いて僕は映画「ブレードランナー」(注4)の中の、つくられた記憶をインプットされ、与えられた古い写真を大事にもってるレプリカントのことを思い出した。
言葉や映像、あるいは事柄としての事件の記憶だけに限れば、知識と記憶は差のないもののようにも思われる。脳の中の情報を、これは知識、これは記憶、と線を引くことにどんな意味があるのだろう。たとえていえば、情報をまとめるときのファイルの組み方、なのだろうか。
僕は記憶というファイルに不可欠なものは「私」に属するある種の「主体性」であると思う。単純に主体性といい切れないのは、無意識や生物的情報をも含めたより大きな「主体性」にかかわるように思えるからなのだ。意識は情報を知識とするが、より広範囲の記憶は無意識と結びついて主体性にかかわるコンプレックスをつくるのである。それゆえ記憶と主体性は卵と鶏の関係のようにもなる。
もし、知識や情報と自分の記憶の区別がつかなくなるならば、そこで見失われたものは記憶そのものでなく、記憶を綴り込む「主体性」というファイルなのである。
建築と素材
ことに建築に関する限り、建築の素材は建築によってつくられる、ともいえるように思う。そのひとつの例は煉瓦である。もともと平たい石を積み上げる、という方法があったとすれば、自然素材の気まぐれなばらつきを避け、土から計画的に生産できる煉瓦が不安定な自然石に置き換えられていくのは自然な成行きである。石積と煉瓦の起源には、地域や文化のさまざまな要因があるだろうが、ここでは建材としての連続した役割に沿ってのみ考える。
自然石を積み上げるという、ある意味で自然の延長線上にあった方法が、文字通り代用品として煉瓦を手に入れる。そこにはある種の「QC」による生産性の向上が見られる。しかし、同時に建築はそこで材料を超えた決定的なものを得るのである。それは思想や文化に計り知れない波紋を投げかけたと思われる、部分と全体、の認識と、単位に基づく物事の構築のことである。建築物の具体的部品としての煉瓦は、積み方の手法、開口の形式、架構方法等を通じてさまざまなスタイルをつくり出してきた。そこでの素材は煉瓦であり、もはや土ではない。そして、煉瓦のような素材によって、歴史の中で現実の建物としてつくり上げてきた形式は、いつの間にかそれ自体がひとり歩きを始めるのである。工法上の意味は煉瓦とまったく異なるタイルを貼る場合にも、タイルの質感と寸法によって、「表現としての組積造」は、多くの人の先入観に入り込んでいる。スペースシャトルを見るまでもなく、建材としてのタイルは表面に貼られて強度や耐久性を得るためのピースにすぎない、ということもできる。表面材としてのタイルは、もともと部分として全体を構築する役目はなく、ただ覆う面積(量)に対する付加価値的デザインに応じて貼られるだけなのである。その点ではある種の外装材を「吹付けタイル」と呼ぶ俗語も、案外本質的な的は外していない言葉なのかもしれないのである。
煉瓦やタイル、コンクリートの打放し、土壁のテクスチャーなど、現実的には限られた工法とさまざまな排除の結果残った表面的な意味が「素材」となった例を、われわれは数多く見いだすことができる。建築の素材は、基本的にレディーメイドなのである。もちろん無数のヴァリエーションや技術的な選択の自由度をもつが、建築を取り巻く社会によってさまざまにコード化された素材や技術が前提となる。言葉や行為のコードと似て、建築もその形式性ゆえに素材にもある種の規範を伴うものなのだ。建築の素材から意味や既成のイメージを完全に取り除くことはできない。したがって建築は、素材や表現において本質的にフェイクを許容するのである。素材表現のフェイクが成立するのは、「本物」というお手本があるからで、その「本物」もまた先代のフェイクとして成りたっている、というような堂々めくりの入れ子関係が、建築の素材にはあるのである。
近代に失われたもの
建築を社会にとって合理的なものとする考え方と、建築に身体的空間を投影し人間の想像力の産物とする考え方は、いつも対立する二党派のように語られてきた。合理←→非合理、あるいはモダン←→ポストモダンのようにである。僕は建築という「物の形式」を考える限り、合理と非合理の同居にさしたる軋轢を覚えない。むしろ、モダニズムを常に合理の側に置いてきた議論に、何やら疑わしい生産社会の自己肯定のカラクリを感じるのである。
アヴァンギャルドであったモダニズムが経済的な生産機構の中に取り込まれ、モダンスタイルとして社会に定着していく過程を、モダニズムの発展というのならば、それは片手落ちではないかと思う。
今世紀の初頭にもモダニズムの前衛たちが形式的にも比喩的にも開いた19世紀的な箱は、まさにパンドラの箱であった。装飾された箱、の中の出来事であたった多くの「下部構造」が、急速に目に見えるかたちとなって表出したのである。
建築物の構造体や剥き出しの機械、人の無意識や肉体、それは建築のみならず、むしろ造形美術やシュールレアリスムの運動の中にスキャンダラスな表現を伴って現れた。それはいい換えれば急速に成長した工業生産社会の余剰が、モダニズムという前衛運動に捌け口を見つけて噴き出した、歴史の断層だったのである。モダニズムは、第一にアヴァンギャルドであり、生産社会の規範というよりは、即物的な合目的性の背後にフェティッシュな身体空間や物のオブジェ性、あるいは形式に対する違反、などの非合理をもつ「過剰」の表現行為、あるいは「欠如」によるフリークであったのだ。そしてその後のモダニズムは、乱暴ないい方をすれば、たて続いた「戦争」という、文字通りの有無をいわせぬ過剰消費によって前衛的な過剰表現の存在理由を失うのである。そして、面積増幅機として社会的に有用な過不足ないモダン(またはポスト・モダン)スタイルの建築物は戦後の都市に均質空間を広げてきたのである。
建築と、都市に飽和する物との区別は希薄となり、建築の環境に対する力は虚弱化した。本質的な差異をもたぬ建築物は社会の制度的、経済的要求に従って役割を与えられ、人びとと共にそれを演じ始めた。人びとは建築を通じて世界を発見する機会を失ったのである。
建築と物の形式
それでも僕は特定の場所に留まって、建築という物あるいは手段によって、世界とまでいかなくても、リアリティをもって身体的なかかわりをもつことのできる豊かな環境を見い出したいと思っている。建築という専門用語を辿れば、身体や感覚的環境と建築物のかかわりに関してバリアフリーとかアメニティなどの言葉がすでに用意されている。それらの言葉の背後にある、住環境の向上に向けた真摯な努力を決して軽んずるものではない。が、それらは身体や室内環境に対するある種の対症療法と認識して、それに重ねてさらに建築、あるいは身体を取り巻く物的環境の全体性を考え、それを豊かなものにしていく視点が必要ではないかと考えている。
同じようなことは建築のプランニングを行う上で、人を点と線、つまり個人と動線としてシミュレーションを行うことの中にも現れているようにも思われる。建築計画の常套的な方法ではあるが、そこで注意したいのは、点で表される個人は、必ずしも主体としての人を意味するのでなく、最小限政治単位〈ミニマルポリティカルユニット〉でしかない、ということだ。ストラテジー、あるいは犯罪事件の現場検証、王座の位置や宴会の席次などを考える場合の点と線である。そして、建築の図象形式(平面図)は、最小限政治単位の容器としてのみ成り立っているわけではないのである。また、主体としての個人は抽象的な空間の中の点ではなく、物的環境の時間や意識をも含めた身体空間にいるのであるから、点と線の明確な区別もまたないのである。ワンルーム、個室群等の議論も、われわれの物的環境をつくる総体的な物の形式とは異なる建築計画上の区別によって行われるのである。
建築物から専門分化した背景や、観念的なメッセージを取り除き、人とかかわる物の形式を考えたいと思い『jt』の片隅を借りて内田祥士と隔月に小さな連載を書いた(注5)。いくつかの事例に添って建築物を物を媒介にした表現ととらえながらも、それらが語るスタイルや意味をあえて離れ、表現の方法論を通じて時代と交錯した建築家の意志や価値観を見い出そうとした試みだった。建築家の作品固有のデザインや建築を取り巻く思想ではなく、その表現に使われた素材や施工技術など「建築」の周辺状況に対して作者がその建築的表現のためになした仕事やその方法を「表現の技術」と呼んだのである。
ここで技術と呼ぶものは、科学技術や建設技術のことではなく、物をつくる個人の手に属する技巧〈スキル〉を伴う仕事のことである。技術とは、謡や舞踏などの芸事や、職人の修行においては自明の事柄ではあるが、具体的な芸や製品をひとつでも「全体」としてつくり上げるのに必要な具体的な方法のことである。ところが専門分化した建築の具体的な物としての全体性は、さまざまな合理的な理由によって非常にわかりがたい物となってしまっているのだ。そして、そこに物を媒介とした表現〈コミュニケーション〉の全体性を成り立たせるものこそ、建築家の表現の技術なのだ。そしてここでいう仕事、技術あるいは技巧は、個人の主体性なしにはあり得ないものである。
建築の代用品
われわれを取り囲む物の環境と混乱と衰退は、物や物による環境を具体的な豊かさとして享受する日常的な方法、あるいは規範をもたないことと、社会や制度の中で曖昧に揺らいでいるわれわれの自信の主体性に拠るところが多いのではないかと思う。物の豊かさとは、商品の豊富さや財産の多さとはもちろん異なる。物を媒体とした人の仕事の成果といい換えてよい。われわれが「自然」と呼ぶものもその大半は人の仕事の結果見い出したものなのだと考えてよいだろう。物にかかわる人の技術や仕事が物の環境を見い出し、それにかかわる人の主体性をも伝えるのである。
「建築」〈アーキテクチャー〉は物を通して見い出された理念や形式である、したがって物が物としてつくられず、架空のマーケットにしたがって商品が生産される社会では、物の背後のアーキテクチャーは希薄になる。その結果都市を埋めつくした物を建築の代用品と呼んだ。そして代用品の生産に関してよく働いた、建築、という社会的にさまざまに専門分化された方法を示すテクニカル・タームは、物を通じて特定の場所と人間が具体的な環境を見い出す、という足許の目的を曖昧にするのである。また、原理や形式ではなく「建築」にかかわる建築家の意識や思想も事態をさらに混沌とさせたのである。現代のカオス的な物の堆積状態の中で「建築」は、その代用品をカテゴライズする架空の規範になってはいないか。
「建築」は現代の形而上学となってはいないだろうか。物の堆積の中で、身体が物とのかかわりを通して環境を見つけ出す。そのフィジカルな出会いの場に際して、建築は傘や自転車ほど有用な道具なのだろうか。現代の物的混沌の中で、身体や意識とかかわりリアルな物的環境をつくる物、われわれが必要としているその物は恐らく「建築」という言葉さえ消し去る、新しい「建築の代用品」なのである。
注1 この問題に関しては神谷武夫の論文「文化の翻訳ム伊東忠太の失敗」に詳しい。『at』1992年11月号,
『燎』No.22に再録。
注2 郊外の工場や事務所、健康ランドの類、コンテナに彩色したカラオケ・ボックス等、オウムの建築物とは
サインによって意味が明示されているか否かの差しかない建造物は多い。
注3 キャリバンはシェイクスピア「テンペスト」に登場する醜い怪物。
注4 リドリー・スコット監督,1982年。アメリカ映画。
注5 「表現の技術」(『jt』1994年6月より1995年7月)。内田祥士と隔月連載。