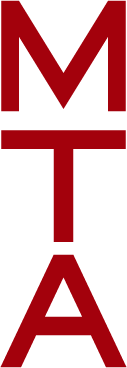Architect
内在する時間としてのディテール
「建築の再生」草稿
時間の堆積
確かにイギリスのSF作家、J.G.バラードの小説のどこかで“時間を内包するゴシックの建築物に対し、未来から来て過去へと経過して行く外的時間の流れのなかに建っている近代建築群・・・”、と言うようなくだりを読んだように覚えていた。古い文庫本をめくって探しては見たものの結局見つからず、出典もセンテンスも曖昧なままなのだが、時間を内包する建築物と時間に外在する建築物という言い回しに興味を引かれて、そこの部分だけをうろ覚えにしていた。
いったい時間を内包するとはどういうことなのだろう。
感覚的にはなんとなく分かるようにも思える。長い時間を掛けて作られたゴシックの聖堂のみならず、途方もない時間と労力によって刻み付けられたインドの寺院建築に見られる透かし彫り等からも、その場に漂っている時間の堆積のようなものを感じることがあるからだ。つまりその様な感覚のことなのだろうとは想像がつく。
例えばひとつの仕事が完成するまでの手間ひまの総量、人間の労働の集積、実際の長い時間を経過してきた風化の痕跡、歴史的知識、その様な事柄の集合がその建築物の空間に独自の時間的感覚を呼び覚ますのだろうか。いやたとえ、人の仕事を抜きにしても、樹齢数千年といわれる古木や古代の廃虚、あるいは人類の営為を超えてなにも変わらなかったかに思える自然の風景等に対峙するとき、我々は一個人の及ばない遥かな時間を思い起こすのである。積み重ねられた仕事の量、にせよ、自然が残した遠大な時間の痕跡にせよ、一個一代の人間の限度を遥かに超える時間によって刻まれたものをを前にするとき、我々はうんざりするような時間のスケール感を覚えるのである。
その様な感覚を我々は、近代または現代の建築物の前に立って受けることはほとんどない。超高層や巨大建築物であれその規模の如何を問わず、辟易するような時間的感覚に眩惑されることはないのである。
まさに(たぶん)バラードの言うような意味で流れる「時間」の傍らに立つ「空間」でしかないのである。建設という行為は、そのなかで様々なプログラムの時間が経過して行く箱を提供することなのだ。
時間と空間、個人と種、自然と人工等の区別は前近代には現在よりも渾然一体となったものだったのではないかと考えられる。恐らくカテドラルのような超絶的な建造物は、その物質的な竣工を超えた神の前での人の営為として、世代を超えて脈々と続けられて来たのだろう。宗教も経済も、時間や空間とならんで人々の営みと不可分のものだったに違いない。建設は農耕等と並んで、始めも終わりもない人々の日々の営為でもあったのだ。
カテドラルのような西欧の大建設物とは打って変わって、紙や木材で出来た江戸の長屋を数百年の長きに渡って維持し続けたのは、落語の世界の定番の登場人物である大工や左官屋である。営繕工事も含んだ建設行為はまた、庶民の日々の営みでもあった。
対して現代社会は、建設産業の発展とともに建築を売買可能な経済の対象物へと変えた。
十分に短い時間で完成する建築物は、個別の財産や建築作品として人の様々な営みや行為の対象物となったのである。そして取り引きに関わるコンフリクトの軽減こそが経済効率を上げる大きな要因となる。特定の場所や、長大な時間を要するものは徐々に淘汰され、一般性を持ち、経済的な建設だけが残されたのである。
社会が、政治、経済、宗教、生活等の区分されたジヤンルの複合体になって行くなかで、建設産業は時間的なファクターを切り捨てて、そこで過ごされる時間を建築以外の他のプログラムに譲り、「空間屋」としての分業を請け負ったのである。
社会資産としての建築
個別の経済対象として建設される建造物も、それが所属する社会の共通の社会資産となる。それは、その建物が個人のものであれ、法人のものであれ、公共のものであれ、変わりはない、はずである。ところが我々のうちの誰が、他人の建築を自分の属している社会の共通の財産だなどと考えているだろう。
建築物の共有財産意識の高いヨーロッパの古い街並みを持った都市などでは、新しく建つ建物にも、色彩や形態の規制が及ぶことがある。
守るべき街並みを持たない、東京の様な都市で一律な形態規制の様なものが役に立つとは思えないが、そのなかでも共有の価値観として受け継いで行くものは何なのかということを、我々は常に意識し続けなければならない。
そして、建築物そのものが、時間の集積場所ではなくなった現在、建設物(建設された空間的環境)に身体的な時間を繋ぎ止めるプログラムを見付け出し、具現化させて行くことが近代建築を正当に、つまり批判的に引き継いで行く我々の義務なのではないかと考えている。
建築は単体では一過性のものとなったが、それらの使い切りの建築物のなかには目に見える形で、あるいは潜在的に、時代の遺伝子のような情報が残されているのである。
その多くは賑やかな表現の背景にある不毛で貧しい我々の建築的環境を伝えるものだが、それらに混じって、未来の建築的環境を豊かな形で実現する可能性をもった技術や考え方が残されていることがある。それらを見落とさずに未来へと伝えることは大事なことだ。
建築が地域に固有のものであったときはその様なことを考える由もなかっただろう。受け継がれて行く建築は、それぞれの職人達の手のなかに「仕事」として伝えられてゆくからだ。
建築の生産が工業化され、建築のデザインも多様化された現在、現場の建築生産者のスキルに社会資産としての建築を伝承させて行くことは望み得ない。
職人の技術を守り、伝えて行くことは大事なことだが、それだけでなく、工業社会の施工技術、特に各サブコンの工場生産上のスキルや、関連する職種の人々が持つさまざまな技術を具体的なものとして残して行くことは重要である。そして、それらを具体化させ、建築に統合させて行くものこそ表現者としての建築家の技術であり「仕事」なのではないかと思う。巧みな仕事によって具現化された空間の表現は、例えその建築が使い切りの耐久消費財として経済社会のなかに投げ出されたとしても、その現場を通過した人々の意識や記憶のなかで受け継がれて行くのである。そのような意味で、建築を社会資産として後世に残す方法は、フィジカルな耐久性を上げる。という方法だけではないように思えるのである。
建築の消費と再生
人の具体的な空間認識のなかで表現にかかわるディテールは大きな働きを示す。
そして、具体的な空間体験は人の五感のさまざまな経験とともに身体的空間として人の意識に刻まれる。これは誰にも経験のある、食事という行為とも同種のものだ。
皿の上の美しい料理は、口に入り、物理的に解体され消費されるそのときに味わわれ、その後それは身体的な栄養とも(毒とも)なる上に、記憶にも刻み付けられる。それにより人は料理を作ることも出来るし、語り合えも出来るのである。
建築は、音楽や皿の上の料理よりは長い時間のなかで消費されるものだ。もちろんその場合消費とは物理的に朽ち果てることを意味してはいないし、音楽や料理の消費とは、音が拡散して消え去ってしまうことや。料理を皿の上から胃に移してしまう行為のみを言っているのではない。体験が記憶となり、他者と共有できる社会的な価値観として持ちえるようになる時間的な過程を消費と考えている。
そして、一個の全体性を持った建築物も部分を通じてしかその全体性は認識し得ない。つまり、身体的な空間に対して建築は常に部分だとも言えるのだ。
世界(全体)への入り口は常に一部でしかないのだ。建築の全体性も部分によって認識され、語られる。建築のディテールは、技術的、審美的、などのさまざまなレベルにおいて考え得るものだ。が、そのなかで、現在最も考えられるべきだと思うのは、時間を視野にいれた人の身体空間と架構された空間を結ぶインターフェイスとしての表層のディテールなのではないかと考えている。そこでは恐らく、建築を消費する手立てとなる物のディテールのみが建築という枷を解き放ち、そしてまた再生することを叶わせる建築の種子となるのである。
ミースが米国に残したいくつかの仕事の中に、われわれはその手がかりを見出せるように思えるのだ。
表層のミース
1919年のガラスのオフィスビル案に始まり、近代建築にミースが送り込んだ、ユニヴァーサルスペースの自動生成ともいうべきプログラムを、「自らを『辺境』へと追い込み、この後『建築』を崩壊させることになる毒ともなるかもしれない」と書いたことがある。(jt9410)実際アメリカに渡ったミースは、一貫して空虚な空間と不毛なまでに美しい表層の輪郭を作り続けた。造形的に空間をデザインするという作業は意図的に放棄されているように思われる。空間のヴォリウム、建築物の外郭は、建物の外因的な計画条件によって求められ、内部はその用途によって仕切のヴァリエーションを持つのみの均質空間で満たされる。建築家の仕事は建築物内外の間に、辛うじて残る輪郭線に自ら追い詰められている。そのぎりぎりの領域に「建築」を消し去ることのなかで、ミースは近代建築を超える解体と再生の萌芽を未来に残したのだとも言える。
それら表層のディテールに、物と身体空間(と時間)を結ぶ手だてが残されているのではないかと思えるのである。
そしてさらに後年のミースは建築の置かれる場所に付いての大きな謎を投げかける。
シーグラムビル(1958)では区画された街区の境界線から大きくセットバックして、あたかも墓石の様に置かれている。高層建築の足許広場として現在は定石ともなった計画手法ではあるが、ピクチュアレスクな基壇形式によって均質のブロックに区画された都市に建築の置かれる場所を特定する試みだったように思えるのである。
1950年に作られたファンズワース邸はある種の建築表現の完璧なモデル化とも言えるかもしれない建築物である。それを以前「古典の形式と工芸的な筆致で描かれたモダニズムの肖像」と書いた(jt9408)。技術的な点や、建築のプラグマティックな諸問題から見れば決して完璧とは言い難い建築物はモダニズムのイコンとなるためだけに細心の注意を払って作られているようにも思える。そしてこの建築物が、広大な敷地と周辺の景観を担保する自然環境を絶対的に必要とすると言う点、時間を逆転させてまで、ミースが実現させたかったものは、建築ではなく風景だったのではないかと僕は考えている。そのような視点はあまりに素人っぽく、建築的視点から見れば非生産的なので語られたことはなかったと思うが、「庭園」という視点は近代建築を超えて表層から建築を再生させる為に有効なものとなるように思われる。
庭園という場所
庭園は自然と人為の境界線の空間に、変化と移動、つまり時間軸を伴って現われる。四季や通り過ぎる時間だけではなく人の視点と移動を伴う時間のことだ。
庭園の多くは、人工的な構造物のほか、植物や流れる水の様な不確定な要素のトリミングを用いて作られる。そこは様々な季節や時間によって異なる様相を表し、またお茶の作法や演奏会のような人為的な行為を伴うこともある。
訪れる人は様々な感覚を動員して自らの時間に沿った身体空間を作り上げて行くのである。
庭園は本質的には開いたものなのである。歴史的に見れば庭園は、支配階級の特権的な所有物の様にも思えるが、それは庭園という形式ではなく、所有という形式がそう見せるのである。モダニズムの興隆期にガーデンシティ、というヴィジョンをともなって提示されたプログラムがすっかり消え去ってしまった背景には、やはり建築を生産者側の表現としてしか理解しなかった経済社会の片手落ちが見られるのである。