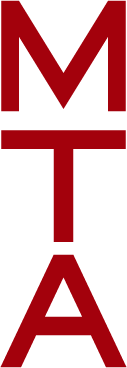Architect
ハードウェアの機能と快楽
NAX BOOKLET 2002年6月 建築金物/細部に宿る住み心地
機械と人間 (シトロエンGSのステアリング)
最近はずいぶん普通になってしまったと言われていますが、シトロエンというフランスの車は、ちょっと奇妙とも言えるような独自のデザインや機械的なシステムで知られていました。ブリキのおもちゃの様な2CVやカエルとも宇宙船ともつかないDSシリーズなどは20世紀の自動車の歴史に欠くべからざる指定席を得ています。それぞれの魅力やユニークさを語るのは別の機会に譲るとして、DSシリーズからAMI6、GSへと続 くシトロエンのユニークな伝統のひとつに、1本スポークのステアリングがあります。スポークというのは、ステアリング、いわゆるハンドルと操舵軸とを結ぶ部分のことです。エアーバッグの普及でこのごろはスポークというより塊になっているようなものも多いのですが、大抵はT型の3本や、左右対称な4本のものが基本の形になっています。
そのスポークが1本だけで、それが直進時に左斜め下、時計で言えば8時の方向についているという奇妙なものがシトロエン伝統のスポークでした。(注1)
なぜかは聞いたこともないし、シトロエンについて書かれた本でも見たことはありません。そのこと自体はシトロエン好きのへそ曲がりの人々にとって常識のように知られていることなのですが、その理由は未だに謎のままです。
(注1)(普通はハンドルの中心付近にクラクションのボタンが付いているものですが、細い1本スポークのシトロエンは付く場所もなく、別のところに付いています。)

けれども僕はある時その理由を確信しました。もう10数年も前に、ドイツのケルンに住んでいて、GSという空冷の小さなシトロエンに乗っていたときのことです。週末にパリまでちょっと出かけようと(ケルンからだと案外気軽に行けるんです)妻と二人でオートルートを走っていました。道はすいていて飛ばせるものの退屈です。背筋を伸ばしてきっちり座り、10時10分にハンドルを握って、なんて長くは続きません。だんだん座り方もだらしなくなり、両手でハンドルを持つのも面倒くさくなってきます。ちょっと斜めに座って左の肘をドアーの肘掛けに載せ、片手でひょいと左の親指をステアリングにかけたとき、僕はおもわずあっと声を挙げてしまいました。左手の親指を、ステアリングと斜めに生えたスポークがつくる入り隅にぴったりと迎え入れられたときのことでした。しまった、やられた!そうだったのか!と隣席で寝ていた妻を起こしてそのことを言わずにはいられませんでした。肘掛けに肘を載せて片手をだらしなくハンドルにかけた、いい加減な運転姿勢を見越して、彼らはその手の行き先にスポークを持ってきたのです。いや、持ってきたのだと思ったのです。
でも本当にそうなのでしょうか。正解は未だに解りません。そのデザイナーは、人がだらしなく、つまり正しくなく機械を操作しようとするだろう、という正しい理由に基づいて直進時に斜め、という奇妙なスポークの位置を決めたのでしょうか。僕は絶対にそうだったのだと確信しています。実際そのデザイナーが意図しなかったとしても、僕はその形を正当化する理由を見つけたのです。
合理的であることが必ずしもひとつの理由だけに拠らないことを僕はシトロエンのステアリングから学びました。
ステアリングのあちら側にはハードな機械の世界があり、こちら側にはときにだらしなくもなる人間の世界があります。機械の機能と人間の操作、そして間をつなぐのがインターフェイスデザインなのです、と言い終われば専門家にとっても、専門家から教育を受けた一般の人々にもに分かり易いエピソードです。
けれどもそれは目に見えるある側面を語っているにすぎません。このエピソードには目に見えない部分があるのです。そしてそれが前提となって、僕は目に見えるデザインの意味が見つけられたのではないかと思っています。
それが何かと言えば機械のタッチ、つまり、手応えや使い心地の部分です。
当時のGSは俊敏に動くのは不得意だった代わり、まっすぐ走る安定性にはとても優れた車でした。長いホイールベースや油圧を使ったサスペンションの機構のおかげで、小さな車で飛ばしている割には、のんびり気楽にオートルートを走れました。斜めの1本スポークにかけた左の親指には、高速であたふた働く車の様子がゆったりと伝えられていました。もちろん車の動きですから指1本だけと言うわけでなく全体から感じるものなのですが、そんな車のタッチのなかだからこそ、だらしなく運転するのが楽なのでしょう。「のんびり」、は 人の側だけの属性ではなく、のんびりさせる機械とのんびりした人間の一対の系をなしていたのだとも言えるのです。
つまり、ここでのインターフェイスデザインは「だらしなくても運転出来る」ための「手段」ではなくて「だらしなく運転する」ための必然的な目的地のひとつだったのです。
デザインを物の形の中だけでなく、物の使い心地を通して考えてみる視点が必要なのではないかと考えています。人の身体に近づくほど、デザインは手段から目的へと向かうのではないでしょうか。僕たちは、見える空間だけでなく、人が物を通して体験する空間についてもっと考えてみる必要がありそうです。
行為とデザイン (シトロエンCXのドアーハンドル)
そしてまたシトロエンを引き合いに出しますが、CXという少し前のモデルの室内には当たり前のような顔をしてユニークなドアーハンドルが付いています。
自動車の室内側のドアーを開けるとき、多くの場合レバーハンドルを手前、この場合はドアーパネルに直角の方向、に引いて拘束をリリースしながら、もう一方の手で手掛けを握ってドアーを外に開きます。大抵両手を使わないと安全確実かつスムーズなドアーの開閉は出来ません。車を傾いた場所に止めたときなど、扉が自重で勝手に開いてしまうと、隣の車に傷を付けたり、通り越そうとする自転車などにとって大変危険です。それで多くのタイプの車はリリースの他に手掛けを設けて扉を保持しながら開閉させようとしているのでしょう。
CXのドアーハンドルにはレバー状のリリースがありません。代わりにリング状のものが扉の吊元側に付いています。けれども、これはレバー状のものと違ってドアーパネルと平行な方向に動きます。肘掛けの端部は握りバーになっていますが、それを片手で握ってもう一方の手でリングを引こうと思うと体使いがいかにも不自然です。ちょっと見にもどう動かすかが解りません。実際降りようと思ってドアーの開け方が解らなかったパッセンジャーの人たちに、僕は何回も説明したことがあります。
まず、楽に座ったポジションのままドア側の肘掛けに沿って、自然に手が掛かる、ぐにゃっとした質感の握りバーを握ります。そのバーを握ったまま人差し指、または人差し指と中指を、ちょうどピストルを撃つような格好にのばします。するとピストルで言うと引き金の位置にあるんですよ。そのリングが。
後は引き金を引くだけ。ドアはいやでもすでに保持された状態で開くのです。
最初はちょっとわかりにくい機構ですが、使い方さえ解れば実に楽で、かつ安全なリリース機構なのです。しかもその動作は片手ですべて出来るのです。

ドアの開閉機構にとっては片手で開けられようが両手で開けられようが差はありません。しかし、恐らくそのデザイナーは、レバーを引きながらの扉の開閉の際、上半身を不自然にねじる、エレガントさに欠けた姿勢をきらったのでしょう。開閉のすべての作業が楽にかけたままの姿勢で行えるCXは、その点でも無理がありません。実際、CX以外の大抵の車は、背もたれを倒したままだと降りるのに一苦労します。
ただし、多少無理な姿勢を取ることで、開閉の際の注意を促す。とか乗り降りの際は背もたれを正して後方の安全確認して降りるべし。とかの合理的説明はいくらでもあることは、建築の設計者である僕にも良く解ります。
けれども面白いのは、人間の体のように、基本的な構造が万人に等しいような規範をもってしても、その使い方や、ドアーの開閉のように単純な仕組みの機械の操作法に説明可能な、つまり合理的な解決策がいくつもある、と言うことなのです。
まず、ホールドさせて、次にそのままリリースしないとドアーが開けられないという、体の使い方を強制するようなこのデザインは、いかにもフランス的あるいはシトロエン的だと思えます。
しかし、さて、これからが問題ですが、シトロエン以外の車はどれも体の使い方を強制しないのでしょうか。
いや、車だけでなく、椅子やテーブル、窓や階段など僕たちを取り巻くあらゆる身体に関わるデザインは体使いを強制していないのでしょうか。
実はそんなことはありません。強制というのはちょっときつすぎる言い方かもしれませんが、僕たちのほとんどあらゆる体使いや振る舞いは、ものの扱いとひとつの系をなしているのです。人の身体に関わるデザインには、「人間の自然な振る舞いに沿ったデザイン」とか「自然な形」などはあり得ません。
人と物は、話し手と聞き手が共通の言語を理解して初めて話が通じるのと同じで、使い手とデザイナーがある文化や認識を共有してこそ、形と働きを身体で結ぶひとつの系を作れるのです。その点では人と物の間にあるインターフェイスデザインは、物の側だけでなく、僕たちの体使いのなかにもあるのです。
CXのドアーハンドルのように、車を降りるという基本的な認識の範囲で、ちょっとひねった解決策を示されたとき、僕たちは改めてそれを発見することが出来るのです。それは毎日使っている言葉のなかで新しい単語を知ったときと同じことなのです。なるほど、と解ってすぐに自然に使えるようになるでしょう?デザインにはそのように日常を発見する力があると思います。また反面、自由な身体の可能性を日常の規範に埋没させる力をも持っているのです。
目に見える形と手に触れる物 (2つのレバーハンドル FSB L-20)
ようやく車を降りて建築にたどり着きました。けれどもまだ中には入れません、玄関のドアーハンドルに手を掛けたまま立ち止まってしまったからです。
ドイツのFSB社のレバーハンドルのスタンダードデザインに1023シリーズがあります。マックス・ビル (注2)のデザインによる定番で、L-20という品番でヤマギワが輸入しています。
僕はこれが割と気に入っていて何度か使ったことがあります。10年くらい前のことですが、ある共同住宅の扉に使ったときにふと違和感を感じたことがありました。その2、3年前に使った物と同じ品番の同じ製品のはずなのですが、ちょっと異なった物のように感じたのです。工業製品が商品としては同じ名称で売られながら内容が変わってゆくことはよくあることです。品質的な点も、形もそれ自体は充分な製品だと思えましたので、その後も使っています。
しかし、ある時期に用いた物とは明らかに異なるところがあるのです。
(注2)(1904~94 スイスのチューリッヒを拠点に、建築家、画家、彫刻家、工業デザイナー、広告デザイナーとして活躍、カタログにはwith Ernst Moekkle[エルンスト メッケル]と記載されています)

まずちょっと見の印象、ほとんど同じ形ではあるのですが、線形が僅かに異なっている。実際各部をノギスで計ってみれば太さの寸法が方向によってコンマ何ミリか違うのですが、まあ同じ形と言える範囲です。しかしさわり心地が全く違うのです。僅かなプロポーションの差もさることながら、形ではなく手触りが気になりました。表面のテクスチャーやバネの反力を比べても判らないのですが、何か軽い、と思わせる手応えだったのです。固定されている物なので 重さは分かりませんし、慣性を感じるほどの大きさや重さの差は無いように思えます。ではどこが違っていたかと言えば、「冷たさ」が減ったことでした。
同じ温度のときに素手で触って比べてみれば判るのですが、古い物の方が冷たいのです。同じ気温のときですから当然温度は同じです。ですから正確には冷たく感じる、つまり掌から奪われる熱量の違いなのです。同じ材料で作られながら熱容量が減った、ということは外観が同じで体積、または質量が減った。つまり軽くなった。と、考える前に感じたのです。
数年前、それをヤマギワの人に尋ねたところ、一時期、鋳造からパイプの絞り加工に製造法が変わっているのでその前後ではないでしょうか、と聞きました。実験したわけではありませんし、メーカーに確認してもいないので技術的な理由は分かりません。
しかし、何らかの理由で肉厚が変わったことは事実なのでしょう。
機械の機能的な部分では、可動部品の軽量化は性能向上につながります。
生産コストの軽減にも結びつくかもしれません。それでも形はほとんど変わらずに「同等品」が出来るのですから、生産者の側から見た場合、そこに何一つネガティブな要因はないとも言えるでしょう。
しかし、ほとんどなさそうなことですが、ユーザーが、レバーハンドルに「熱容量」を求めていたならば、商品性としてはどうだったのでしょうか。
「熱容量」などと考える人は、まず、いないとしても「重厚感」とか「高級感」とかを求める人は多いはずです。
さしたる理由もなく、昔は良かったと言う人がいます。単なるノスタルジーの場合も多いのですが、その体感的な差を言葉にする科学的な術がない場合も多いのではないかと思います。
住宅や、僕たちの身の回りの環境を占めるさまざまな工業製品に、「クォリティー」という言葉が多く使われています。が、大抵は生産者側の技術的な基準を示すものにすぎません。ユーザーにとっての物の「使い心地」や「タッチ」について、技術的な言葉で要求できる基準はなかなか見つけられません。
物は生産者が、形はデザイナーが、支払いはエンドユーザーが受け持つ中で、日常の使い心地やタッチを、生活者が生産者に伝えられないのはおかしなことです。感性や身体に訴えるものを、経験を超えて科学、あるいは技術として、産業にフィードバックさせることが出来る技術者や設計者が必要な時代になってきたのかもしれません。
ハードウェアの機能と快楽
建築金物のことをHARDWAREと言います。よくハードとソフトなどと対にして言われることのある、「ハードウェア」です。金物や道具のみならず、機械物一般というも意味もあります。近代は機械の時代と言われて、ダイナミックな機械へのオマージュから、流線型やハイテックなどの様々なスタイルやビジョンを作り出して来ました。反面「モダン・タイムス」に見られるような、暴力的で非人間的な悪いイメージも機械は持っていました。どちらも機械そのものではなく、機械のイメージに対する表現であることが、まさに20世紀でした。機械時代が生んだあまりにも多様な機械のイメージが機械を覆い尽くし、機構が見えない機能の時代に、僕たちは来てしまっています。
けれども、消えてしまったわけではなく、様々な局面で僕たちの生活の「質」を支え、感じさせているものは、まぎれもないハードウェアなのです。
抽象的な機械一般と言うことではなくて、住宅や家具、あるいは道具のように身の回りで、人の動きを伴って働く機能を持った物のことです。
それらはイメージだけでなく、実体の物を通して僕たちの体に働きかけ、
日常の中での、扉の開け閉て、窓の開閉、引き出し、収納扉、住宅の中に限っても、僕たちの日常の様々な動きに様々な物が関与して、当たり前の日常行為が何者かによってデザインされています。もちろんその「何者か」はデザインする人だけとは限りません。習慣的な反復の結果や、生産技術の紋切り型などから来るものもあります。しかし、それらは形ばかりでなく、タッチや手応えすべてが無意識のうちに、日常の身体や運動に刷り込まれているのです。僕たちの身体に関わる物やデザインは、僕たちの体や運動をも含めたそれぞれの機能系を作っているからです。そして、物の質感や手応えは使い心地に大きな影響を与えます。
市販されている製品の中にはタッチや質感が売り物の商品も少なくありません。たとえば、聞くところによると、かつてのアメリカの自動車生産ラインには、ドアの開閉音をチェックする係りがいたそうです。なるほど、音も大事な質感です。同じようにベンツのドアの剛性感などは、商品性の大事な部分を成しているように思えます。写真のへたくそな僕も、見た目とシャッター音などの、機能に関係ない、快楽の部分につられて不要なカメラを買った覚えがあります。人に使われる物は、現実の機能にも増して、使い心地の快不快が価値を決める場合もあるのです。そして、人の気持ちをより豊かにするものは、そんな物の感性に触れる部分にあるのではないかと思っています。
料理の機能は栄養補給で、快楽は味なのだと思えばあまりに当たり前のことのようにも思えてきます。
けれども脚触りや手触り、動きの手応えやタッチというような、住宅の「体感デザイン」について語られることが少ないのはいったい何故なのでしょうか。
個人の感覚的な部分なので基準化しにくいこともあるでしょうが、それだけでなく、建物の売り買いのされ方に起因している部分もありそうです。
自動車やカメラなら、気に入らない物を買わない自由がありますが、建物の売買では、あまりその自由はありません。ローンや契約の関係で、一度に目をつぶって買い入れなければならないからです。
建設産業に、特に顕著なことですが、今の日本の物づくりは、作り手側の都合に偏りすぎているようにも思えます。特に建築や、僕たちの身の回りに関わる物は、物の機能的な側面だけでなく、使い心地やタッチというような、使う人の感覚的な経験を、より豊かにするように作られてほしいと思います。
人が物と作る関係には、機能と快楽が同居しているのです。快楽と言えばちょっとハードな言い方ですが、快適、楽しく、質感やテイストを持ったものと言うことです。
生活者には、衣服や食事のように、物や空間の肌触りをもっと意識してほしいとも思います。建築だから宛行扶持(あてがいぶち)で我慢しなければならないことはありません。
仕事となると生産者側の専門家になりがちな、設計者やデザイナーも、ひとりの生活者として、自分の身体や感覚にリアリティーを持ち続けなければならないと思います。日本の近代や、敗戦後の復興を支えてきた多くの産業が置き忘れてきたのは、人のための物づくりなのかもしれません。