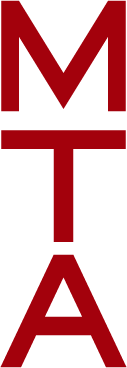Architect
大小飛び道具
2009年1月
30代から50代の現在も、ある時期から僕の生活と仕事の傍らに常にいた車のことを書きたいと思います。いずれは無くなるただの車のことにすぎませんが、仕事や家族、僕個人の楽しみに欠かせなかった、お気に入りの生活道具でした。
CXというシトロエンのセダン、パンダというフィアットのコンパクトカーそしてエリーゼという名のロータスのスポーツカーがその3台です。
車好きの人と話す機会があると、僕はそれらの車を「池波正太郎風に言うと」と前置きして「大小飛び道具」と呼んで自慢しています。大は今ではそれほど大きくはない部類のCX、小はパンダ、飛び道具はエリーゼのことです。
珍しい共通点は、3台ともすべてワイパーが1本、というところだけです。
シトロエンCX2500 PALAS IE 1985年登録(1988年より現在) 型式 E-MANG
具体的にシトロエンにはまったのは妻と二人でドイツに住んでいたときに乗っていたGSという小型車からでした。ですから現在のCXは2台目のシトロエンになります。GSも素晴らしい車でした。
具体的にと断ったのは、20世紀の自動車神話のひとつとも言えるID・DSに始まる幾つかのシトロエンに対する「イメージとしての興味」はずっと持っていたからです。小学生の頃に見た、当時の日本の自動車とはかけ離れたDSの異様な姿や、高校生の頃に見たCXの美しい後ろ姿には他の自動車とは一線を画した特別な印象を持っていました。
CXは美しい車です。シトロエンの社内デザインによるものですが、ピニンファリーナの
デザイナー、レオナルド・フィオラバンティのスケッチと彼がBMC(British Motor Company)
のために作ったベルリーナというデザインプロトタイプ・カーが原型になっているようです。
デザインは美しいだけではなく、人の身体の使い勝手を考えた優れた形を随所に見ることが出来ます。そのあたりのことに付いては、このHP上にも出していますが、以前INAXBookletに「ハードウェアの機能と快楽」という文章で書きましたのでここでは省きます。その他にもハイドロニューマティックの機構や乗り心地など、シトロエンを取り巻く言説は賛否両論を含め多いのですが、それらについては自動車雑誌のバックナンバーやシトロエンについて書かれた本に及びませんし、蘊蓄の受け売りはきりがないので、止めておきます。
それでは何を書くのかと言えば、「僕が彼女を好きな理由」のような、個人的なオマージュにならざるを得ません。21年以上乗り続けていて、いつ他の車と比較しても代わりになるものが無かったのですから、好きだったのです。
その一つの理由「美しさ」は前にも述べましたが、僕が高校生の頃の1970年代、「自動車」がまだ若く元気だったときに見た美しさに今でも捕らえられているのだと思います。何の疑いもなく「人生を豊かにする道具」として考えられていたのではないか、という印象を僕は持っています。
次の理由は感触です。大きくは乗り心地や動かしたときの身体へのリアクション、小さくは各部の触り心地や奇妙な質感などです。
椅子の座り心地は、僕の知る限り、自動車の椅子として最高のものです。
但し、CXという機械と自分の身体という系に対して という条件付き、つまりCXで動く場合に、ですからシート単体の座り心地ではないのです。
柔らかく沈むシートです。CXは最近の車ほどではないのですがウィンドシールドが寝ているので他の車より少し後ろに倒したポジションが快適です。
また、もうひとつは、長距離を走るのにこれほどリラックス出来る車はないと思えるほどの走行安定性です。現代の基準から見れば、まったく高性能ではなく、うるさい類の車とも言えますが、スタビリティの高さとフロントアクスル回りの剛性感、路面や車の状態のインフォメーションに富んだ手応えは他に類が無く、他の車に変えられない大きな理由の一つになっています。
セルフセンタリングするステアリングやストロークのほとんど無いブレーキのタッチ、
エンジンを掛けるとムクムクッと立ち上がるハイドロニューマティック独特の挙動は、それ自体の善し悪しとは別に、CXを他と比較できない大きな特徴となっています。もちろん僕はそれらが大変気に入っています。
これは好きな理由とは違うのですが、CX PALLAS IEが最後のシリーズⅠつまり最後の純血シトロエンであるのも贔屓の理由のひとつなのかもしれません。
これを最後にCXはシリーズⅡにマイナーチェンジされ、プジョーグループのなかでだんだんと混血化され、細部のデザインも「より普通」になって行きます。
プラットフォームの共通化やOEMによるヴァリエーション化は現代の自動車産業では常識ですが、CXにはそのようなユニヴァーサル化以前に見られた「メーカーと製品」の
アイデンティティを感じます。
また、ヨーロッパの自動車メーカーには籍を置く都市の名と結びつけて語られることも多いメーカーがいくつかあります。
「国家」よりも「都市」を選びたい僕にとって「フランス」以上に「パリ」と結びつくシトロエンのイメージは、車に付いてきた大変好ましいアイデンティティのひとつでした。
ちなみに僕のCXの色は黒、内装はグレーのファブリック。バルブは黄色のH4走行距離は1988年に手許に来たときの27000kmから、2008年現在は140000kmまで走りました。
ほぼ、娘と同じくらいの付き合いになるCXなのですが、いったいいつまで一緒にいられるのか ? などともたまに思いますが・・・
ま、余計なことは考えないで日々を大切に楽しく過ごすことが大事なのだと考えるようにしています。
フィアット・パンダSELECTA 1992年登録(1993年~2007年) 型式 E-141A2
フィアット・パンダFIRE 1994年登録(2005年より現在) 型式 E-F141B3
パンダについて書くのは少し複雑な思いがあります。
というのも長く付き合ってきた個体を壊してしまったからです。
17万キロを直前にして、もらってくれるひとが決まった直後のことでした。
今乗っている個体もすでにそのときには僕の手許にありましたが、その車も親友の突然の死により、形見として残されたものでした。
しかし、残念な思い出や悲しい物語があったとしても、いつでもパンダは楽しくて役に立つ車でした。
特に初めのパンダは右ハンドルでオートマティック(E-CVTという富士重工製のベルト式無段階変速機)だったので実に便利でした。
「エンジン付き車椅子」と呼んでいたくらい、あまり良いことではないのですが、200メートル以上の用であればいつでもすぐ動かしていました。
何が良いかと言えばやはり「デザイン」です。かっこいいとかスタイリッシュだとかいうことではなく、「必要最小限」という魅力的なテーマの解答としてこれ以上ないほど密度の高い答えが用意されている解答例なのです。
建築家であれば誰でも知っていなくてはならない「最小限住宅」というテーマがあります。
それに類する最小限自動車の最適解のひとつだと思います。
デザインは初代ゴルフのデザインもした、ジョルジャット・ジュージャロというイタリアの高名なデザイナーです。彼自身一番気に入っている仕事と言っているように、限られた条件の中でのそのデザイン密度は極めて高いものです。
小さな空間に、必要十分な機構と居住性、実用性、操作性が、よくぞ、と思うほど見事に無理なく納められています。
結果としてのかっこよさもスタイルも兼ね備えていると思いますし、それ以上に美しい車であるであることは間違いないと僕は考えています。
初めのパンダ(SELECTA)も現在のもの(FIRE)も初代オリジナルのパンダと基本的なデザインは変わりませんが、エンジンやサスペンション、リアシートの形式などは大きくモディファイされています。
ちなみに初期型のリアシートは、ハンモックのような吊り下げ式のユニークなものでしたが、現在は普通の折りたたみ式になっています。
生産年次に2年の差があるSELECTAとFIREは基本的には同じ時期のモデルですが、雰囲気やディテールは微妙に異なっています。
僕のSELECTAは、ほぼ全世代のパンダに付いている「サイドプロテクションモール」が無い、のがデザイン上の大きな特徴でした。内部はボディーと同じ塗装の鋼板むき出しの部分とファブリックで作られています。
そのファブリックがブルーとグリーンを基調にした多色柄で、ひところのミッソーニのニットを思わせる、極めてセンスの良いものでした。
ボディーカラーはメタリックグリーンでしたので、内装とは実によく合っていました。
FIREはターコイズブルーのボディーにグレーを基調にした内装です。
SELECTAではプラスティックのままだったトランクの棚(蓋)が、モケット調の繊維で仕上げられていたり、鉄パイプのままだったサイドブレーキレバーにブラスティックのグリップが付いたりと、プラグマティックだったデザインが、僅かに「商品性」を帯びてきています。
けれども基本的に、道具に徹した美しさと健康さは失っていません。
質素な車ではありますが、基本的なデザイン密度の高さが美しさを顕しているので、貧乏ったらしさを微塵も感じさせないのです。
バンダは小さい車ですが、便宜的に作られているところが一切無く、「フルサイズ」の使用が前提となっているところが素晴らしいところです。
前席のみならず、後ろのシートも十分な大きさがあり、大人4人で十分に使うことが出来ます。高めのギア比とサスペンションによるものか、長距離も楽にこなせます。リアシートをたためば、相当な量の荷物も運べます。
ひとには勧められませんが、二人の子供が小さかった頃、スチールメッシュの棚でトランクルームを「2階建て」のベッドにして上下に子供を寝かせながら遠くに出かけたりしていました。
パンダは、ついそんな使い方をしたくなるような車です。2階(上部)の棚で寝かされていた息子は、もはや僕より大きく、この1,2年のうちにFIREパンダを運転しそうです。まさか、彼の子供(つまり僕の孫?!) をトランクに寝かして出かけることにはならないでしょうが。
ロータス・エリーゼ S 1 1998年登録(1998年より現在) 型式 不明
僕くらいの年代の車好きの方にとって、エリーゼの出現は20世紀末の事件のひとつとなったのではないでしょうか。
70年代のいつからか消えてしまったライトウェイトスポーツカーというジャンルの 信じられない復活だったからです。
スーパーカーといわれる、どちらかといえば人より機械に重きを置いたオブジェ的な車は数々現れました。
しかし、量産された乗用車のエッジに生まれたMAZDA MX-5を微妙な例外としても、往年のエランのように、車と人が共にあって一つの素敵なスポーツ空間を作り出す、そんなスポーツカーは絶えて久しく現れませんでした。
そこに、しかも、ロータスから現れたのがエリーゼでした。
結果としてエリーゼはエランとは異なる時代の異なるジャンルの車だったのですが、今後、確実に「エリーゼのような」といわれる一つのジャンルを作り出したと思われます。
「お洒落なスポーツカー」というイメージはエリーゼS1にはありません。
どちらかといえばスポーツ・ギアと呼ぶような道具に近いものだと思います。
デートにはとてもお勧め出来ません。
外観は、ある意味すごく格好良いのですが、不思議な雰囲気を持っています。
20世紀的スポーツカーのコンテクストを、随所に思い起こさせる既視感にあふれていながら、現実的にはエリーゼ以外に見たこともない、唯一無二の感覚を作りだしています。
その不思議な感覚は、この車の構造的な成り立ちによるものかもしれません。
通常の自動車のスチールモノコックボディはそれ自体が構造体ですが、 エリーゼのボディは、完結したアルミモノコックフレームのシャシーに被せたカバーに過ぎません。機能的には空力性能を向上させる、ライトやウィンカーなどの保安機器を支持する、という車として必要な役割は果たしていますが、静的な構造体としては不要なものです。
エランもY型スチールバックボーンフレームにエリーゼと同じFRPのボディを被せた構成でしたが、ボディは人の居場所を作るために不可欠な働きをしていました。それに対してアルミの引き抜き材を箱状に接着(!)して作られたエリーゼのシャシーは、シートとステアリングを付ければ、それだけで走ることも出来そうです。
そのせいでしょうか、エリーゼはすぐにS2へとモデルチェンジされましたし共通のシャシーから様々なヴァリエーションも生まれています。
エンジンすらローバーのものからトヨタ製に変わっています。
特異性と既視感の同居するS1のデザインも、オリジナルデザイン自体が「商品性」のためのヴァリエーションにすぎなかったのかもしれません。
そんな印象がエリーゼの外観からは感じられるのです。
きっと、スポーツカーの目標は「自動車」の先にある、ということを彼らは知っていてそうしたのではないかと僕は思っています。
そのあたりの戦略は実にロータス的とも言えそうです。
量産される乗用車では、商品としてパッケージされた全体が商品性を作るのでとても出来ない手法ですが、スポーツカーに限定された商品体系の中では、 レーシングカーのように目的やクラスに合わせた作り替えが通用するからです。
バスタブ型アルミモノコックフレームにサブフレームを介してエンジンや足回りを取り付けて、カウリング(非構造体のFRPボディー)で覆う という優れたアーキテクチャーが、エリーゼとその系列モデルを成り立たせています。
シャシーデザインはリチャード・ラックハム。ボディー(エクステリア)デザインはジュリアン・トムソン。
いずれもロータスの社内デザイナー、エンジニアだそうです。
エリーゼのような車を「物それ自体」で評価することは、意味がありません。骨董品として取って置いても価値のない車だと思います。
モータースポーツという周辺環境や、運転する人の感覚、つまりスポーツとしての使用や、チューニングを前提として成り立つ、動的な世界のためのアーキテクチャーを持った車だからです。
「どちらかというとスポーツ・ギア」と書いたのもそのことに他なりません。
従って、異なる種類のエンジンを搭載しても、異なるデザインのカウルを纏ってもエリーゼに変わりはないとも言えます。また。元々、オリジナルの個体に「物」として求めるエリーゼはないのだ、とも言えるように思います。
きっと、様々なチューニングや使用状況、ドライバーのスキルに応じて、様々なレベルで「走らせて楽しい」エリーゼがいるのでしょう。
僕のエリーゼは、S-1ごく初期のイエローメタリック、5ナンバーの車です。
型式が「不明」なのは正規に登録される以前の並行輸入車だったからです。
その個体も、この10年の間にずいぶん初期仕様と異なってきています。
それでも「エリーゼらしさ」、は益々高まっているのは不思議なことです。
車という「物」に託されて「物」を超えた優れたアーキテクチャーがその感覚を支えているのは間違いない、と僕は考えています。